ペロブスカイト型Mn酸化物の
高分解能光電子分光による
電荷整列ギャップの観測
(東大工、JRCATの十倉先生のグループとの共同研究です)
Physical Review B vol.59,
p.15528 (1999).
はじめに
 ペロブスカイト型Mn酸化物は巨大磁気抵抗効果を示すことから、純粋科学的興味のみならず応用面においても近年大きな注目を集めています。3次元ペロブスカイト構造(ABO3という組成、ここでMnはBに相当します。)をとるLaMnO3はMnイオンが形式的に+3価でd電子数は4.0となった反強磁性絶縁体です。しかし+3価のLaイオンを一部+2価のSrイオンに置換するとMnのd電子数は4.0という整数からずれて小さくなります。すなわちホールが注入されます。するとLa1-xSrxMnO3でx>0.15という組成では強磁性金属に変化します。このMn酸化物における強磁性は古くから二重交換相互作用によるものと考えられてきましたが、それだけでは説明ができないという説もあり最近再び研究が活発に行なわれています。一方、Laイオンをよりイオン半径の小さいNdイオンに変えたNd0.5Sr0.5MnO3
(x=0.5)は約160Kで強磁性金属−電荷整列反強磁性絶縁体転移を起こす事が知られています。この「電荷整列」は上記のLaMnO3の反強磁性体とは違うタイプ(CE型と呼ばれます)で、電荷・スピン・電子軌道の3つが同時に整列するという珍しい現象です。しかし組成が僅かにずれたNd0.53Sr0.47MnO3
(x=0.47)は電荷整列を示さず、低温まで強磁性金属です。 このようなMn酸化物にたいして光電子分光がこれまで行われていますが、強磁性金属−電荷整列絶縁体転移による光電子スペクトルの変化はこれまで観測されていませんでした。また、希土類イオンであるLa,
Nd等の電子状態は殆ど調べられていませんでした。そこで私たちはこれらの系に対して共鳴光電子分光及び高分解能光電子分光を行い、電子状態を調べました。この「共鳴光電子分光」というのはあるイオンの価電子状態を調べるのに有力な実験手法で、後で紹介するするようにNd
4f軌道の電子、Mn 3d軌道の電子といった特定の電子のスペクトルへの寄与を選択的に増大させるので、電子状態を元素選択的に調べる事ができます。
ペロブスカイト型Mn酸化物は巨大磁気抵抗効果を示すことから、純粋科学的興味のみならず応用面においても近年大きな注目を集めています。3次元ペロブスカイト構造(ABO3という組成、ここでMnはBに相当します。)をとるLaMnO3はMnイオンが形式的に+3価でd電子数は4.0となった反強磁性絶縁体です。しかし+3価のLaイオンを一部+2価のSrイオンに置換するとMnのd電子数は4.0という整数からずれて小さくなります。すなわちホールが注入されます。するとLa1-xSrxMnO3でx>0.15という組成では強磁性金属に変化します。このMn酸化物における強磁性は古くから二重交換相互作用によるものと考えられてきましたが、それだけでは説明ができないという説もあり最近再び研究が活発に行なわれています。一方、Laイオンをよりイオン半径の小さいNdイオンに変えたNd0.5Sr0.5MnO3
(x=0.5)は約160Kで強磁性金属−電荷整列反強磁性絶縁体転移を起こす事が知られています。この「電荷整列」は上記のLaMnO3の反強磁性体とは違うタイプ(CE型と呼ばれます)で、電荷・スピン・電子軌道の3つが同時に整列するという珍しい現象です。しかし組成が僅かにずれたNd0.53Sr0.47MnO3
(x=0.47)は電荷整列を示さず、低温まで強磁性金属です。 このようなMn酸化物にたいして光電子分光がこれまで行われていますが、強磁性金属−電荷整列絶縁体転移による光電子スペクトルの変化はこれまで観測されていませんでした。また、希土類イオンであるLa,
Nd等の電子状態は殆ど調べられていませんでした。そこで私たちはこれらの系に対して共鳴光電子分光及び高分解能光電子分光を行い、電子状態を調べました。この「共鳴光電子分光」というのはあるイオンの価電子状態を調べるのに有力な実験手法で、後で紹介するするようにNd
4f軌道の電子、Mn 3d軌道の電子といった特定の電子のスペクトルへの寄与を選択的に増大させるので、電子状態を元素選択的に調べる事ができます。
実験結果及び考察
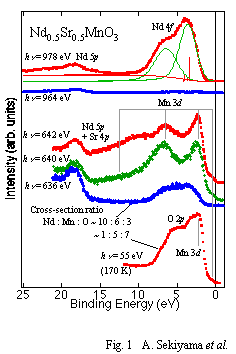 試料は東大工学部及びJRCATの十倉先生のグループに提供していただきました。まずx=0.5に対してMn
2p-3d 及びNd 3d-4f 共鳴光電子分光をつくばにある高エネルギー加速器研究機構にある放射光施設Photon FactoryのBL-2Bで行いました。その結果を右に示します。右図の一番上にあるNd
3d-4f共鳴光電子スペクトルは主にNd 4f電子状態を反映したもので、フェルミ準位(化学ポテンシャル)から測った結合エネルギーにして3.5
eVにピークが、7 eVに肩構造が見られます。このような形状は+3価のNdイオンの特徴であり、0 eV(フェルミ準位、EF)付近には強度がないこととも合わせてNdイオンが+3価である事を確認しました。一方で、この形状はNd
4f 電子がO 2p 電子と強く混成している事も示しています。この形状を2つのピークに分離して解析する事でNd 4f準位を4.7
eVと見積もりました。 また、真ん中の3つのスペクトルがMn 2p-3d共鳴スペクトルです。3つのうち上の2つは下のhn=636eVのスペクトルに比べて強度が増大していますが、これがMn
3d電子の寄与になります。この増大は2.3 eV, 6.7 eVにピークを作っており、その形状はMn 3d電子がO 2p電子と強く混成している事を示しています。
試料は東大工学部及びJRCATの十倉先生のグループに提供していただきました。まずx=0.5に対してMn
2p-3d 及びNd 3d-4f 共鳴光電子分光をつくばにある高エネルギー加速器研究機構にある放射光施設Photon FactoryのBL-2Bで行いました。その結果を右に示します。右図の一番上にあるNd
3d-4f共鳴光電子スペクトルは主にNd 4f電子状態を反映したもので、フェルミ準位(化学ポテンシャル)から測った結合エネルギーにして3.5
eVにピークが、7 eVに肩構造が見られます。このような形状は+3価のNdイオンの特徴であり、0 eV(フェルミ準位、EF)付近には強度がないこととも合わせてNdイオンが+3価である事を確認しました。一方で、この形状はNd
4f 電子がO 2p 電子と強く混成している事も示しています。この形状を2つのピークに分離して解析する事でNd 4f準位を4.7
eVと見積もりました。 また、真ん中の3つのスペクトルがMn 2p-3d共鳴スペクトルです。3つのうち上の2つは下のhn=636eVのスペクトルに比べて強度が増大していますが、これがMn
3d電子の寄与になります。この増大は2.3 eV, 6.7 eVにピークを作っており、その形状はMn 3d電子がO 2p電子と強く混成している事を示しています。
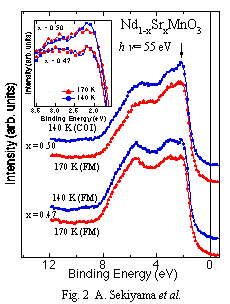 次に金属(Ferromagnetic
Metal, FM)−電荷整列絶縁体(Charge-Ordered Insulator, COI)転移を起こすNd0.5Sr0.5MnO3
(x=0.5)と電荷整列転移を起こさず低温まで金属であるNd0.53Sr0.47MnO3
(x=0.47)の両物質に対して、価電子帯高分解能光電子分光を光の励起エネルギー55 eV(波長に直すと約230オングストローム)、分解能45
meVで測定しました。実験はPhoton Factory BL-3Bで行いました。その結果のうち広いエネルギースケール(結合エネルギーでフェルミ準位からその下12
eVまで)のスペクトルFig. 2を右に示します。このエネルギースケールでみると第一印象としては両物質に違いはあまりなく、またx=0.5でも相転移によるスペクトル変化は大きくありません。しかし、結合エネルギー2.3
eVのピークをみるとx=0.5の温度140 K(絶縁相(COI相))では170 K(金属相(FM相))と比べるとシャープになっています。これは絶縁相でMn
3d電子が局在化した為と考えることができます。このような変化はx=0.47でははっきり見えません(挿入図)。
次に金属(Ferromagnetic
Metal, FM)−電荷整列絶縁体(Charge-Ordered Insulator, COI)転移を起こすNd0.5Sr0.5MnO3
(x=0.5)と電荷整列転移を起こさず低温まで金属であるNd0.53Sr0.47MnO3
(x=0.47)の両物質に対して、価電子帯高分解能光電子分光を光の励起エネルギー55 eV(波長に直すと約230オングストローム)、分解能45
meVで測定しました。実験はPhoton Factory BL-3Bで行いました。その結果のうち広いエネルギースケール(結合エネルギーでフェルミ準位からその下12
eVまで)のスペクトルFig. 2を右に示します。このエネルギースケールでみると第一印象としては両物質に違いはあまりなく、またx=0.5でも相転移によるスペクトル変化は大きくありません。しかし、結合エネルギー2.3
eVのピークをみるとx=0.5の温度140 K(絶縁相(COI相))では170 K(金属相(FM相))と比べるとシャープになっています。これは絶縁相でMn
3d電子が局在化した為と考えることができます。このような変化はx=0.47でははっきり見えません(挿入図)。
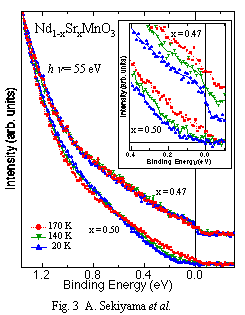 今度は物質の電気的、磁気的性質を主に決定づけているフェルミ準位近傍(結合エネルギー0
eV付近)における、測定温度を変えて測定したスペクトル(右図、Fig. 3)を紹介します。相転移を起こさないx=0.47では20 K, 140 K, 170 Kでスペクトルは殆ど変化せず、フェルミ準位のところでスペクトル強度が不連続的に0になりました(挿入図をみると分かりやすいのですが、この不連続性は温度が低いほど顕著になります)。実はこの「フェルミ準位における有限の強度かつ不連続的に強度が0になる」振舞いが、金属に見られる重要な特徴です。ひるがえってx=0.5のスペクトルに注目しますと金属状態である170 Kではフェルミ準位で有限の強度が見られます(挿入図)。しかし、絶縁体になった140
K及び20 K(転移温度は約160 K)ではその強度が著しく減少して殆ど0になっています。これは「電荷整列ギャップ」が開いた証拠といえます。また、同じ絶縁相でも140
Kと20 Kではスペクトルが僅かに異なり、フェルミ準位近傍の積分強度は140 Kの方が僅かに大きいです。これは140 Kでは電荷整列ギャップがまだ完全に開ききっていない事を示しています。20 Kにおけるギャップの大きさは少なくとも100 meV (0.1 eV)という大きさであることもこれで分かります。このようなCE型電荷整列ギャップが光電子分光で観測されたのは、この実験が世界で初めてです。また、この相転移を起こす組成に非常に近いNd0.53Sr0.47MnO3
(x=0.47)で低温まで金属的なスペクトルが得られたのもこの実験が初めてです。これらの事から、x=0.5ではMn 3d電子数が形式的に3.5と半整数になり電荷整列を極めて起こしやすくなっているところに、x=0.5からみて少しだけ電子が注入されたx=0.47では注入された電子によって二重交換相互作用が強くなり、金属的性質が復活していると捉えることができます。
今度は物質の電気的、磁気的性質を主に決定づけているフェルミ準位近傍(結合エネルギー0
eV付近)における、測定温度を変えて測定したスペクトル(右図、Fig. 3)を紹介します。相転移を起こさないx=0.47では20 K, 140 K, 170 Kでスペクトルは殆ど変化せず、フェルミ準位のところでスペクトル強度が不連続的に0になりました(挿入図をみると分かりやすいのですが、この不連続性は温度が低いほど顕著になります)。実はこの「フェルミ準位における有限の強度かつ不連続的に強度が0になる」振舞いが、金属に見られる重要な特徴です。ひるがえってx=0.5のスペクトルに注目しますと金属状態である170 Kではフェルミ準位で有限の強度が見られます(挿入図)。しかし、絶縁体になった140
K及び20 K(転移温度は約160 K)ではその強度が著しく減少して殆ど0になっています。これは「電荷整列ギャップ」が開いた証拠といえます。また、同じ絶縁相でも140
Kと20 Kではスペクトルが僅かに異なり、フェルミ準位近傍の積分強度は140 Kの方が僅かに大きいです。これは140 Kでは電荷整列ギャップがまだ完全に開ききっていない事を示しています。20 Kにおけるギャップの大きさは少なくとも100 meV (0.1 eV)という大きさであることもこれで分かります。このようなCE型電荷整列ギャップが光電子分光で観測されたのは、この実験が世界で初めてです。また、この相転移を起こす組成に非常に近いNd0.53Sr0.47MnO3
(x=0.47)で低温まで金属的なスペクトルが得られたのもこの実験が初めてです。これらの事から、x=0.5ではMn 3d電子数が形式的に3.5と半整数になり電荷整列を極めて起こしやすくなっているところに、x=0.5からみて少しだけ電子が注入されたx=0.47では注入された電子によって二重交換相互作用が強くなり、金属的性質が復活していると捉えることができます。
さらにスペクトルを理論計算等と比較するとMn 3d 電子の電子相関が強い、Mn 3d電子同士のクーロン反発がバンド幅に比べて無視できない程大きいという事も分かります。すなわちこれらの物質については、単純なバンド理論が適用できないという事です。このような「強相関電子系」の特徴というのは、「高温超伝導物質」である一連の銅酸化物にも見られるものです。
- Akira Sekiyama

 ペロブスカイト型Mn酸化物は巨大磁気抵抗効果を示すことから、純粋科学的興味のみならず応用面においても近年大きな注目を集めています。3次元ペロブスカイト構造(ABO3という組成、ここでMnはBに相当します。)をとるLaMnO3はMnイオンが形式的に+3価でd電子数は4.0となった反強磁性絶縁体です。しかし+3価のLaイオンを一部+2価のSrイオンに置換するとMnのd電子数は4.0という整数からずれて小さくなります。すなわちホールが注入されます。するとLa1-xSrxMnO3でx>0.15という組成では強磁性金属に変化します。このMn酸化物における強磁性は古くから二重交換相互作用によるものと考えられてきましたが、それだけでは説明ができないという説もあり最近再び研究が活発に行なわれています。一方、Laイオンをよりイオン半径の小さいNdイオンに変えたNd0.5Sr0.5MnO3
(x=0.5)は約160Kで強磁性金属−電荷整列反強磁性絶縁体転移を起こす事が知られています。この「電荷整列」は上記のLaMnO3の反強磁性体とは違うタイプ(CE型と呼ばれます)で、電荷・スピン・電子軌道の3つが同時に整列するという珍しい現象です。しかし組成が僅かにずれたNd0.53Sr0.47MnO3
(x=0.47)は電荷整列を示さず、低温まで強磁性金属です。 このようなMn酸化物にたいして光電子分光がこれまで行われていますが、強磁性金属−電荷整列絶縁体転移による光電子スペクトルの変化はこれまで観測されていませんでした。また、希土類イオンであるLa,
Nd等の電子状態は殆ど調べられていませんでした。そこで私たちはこれらの系に対して共鳴光電子分光及び高分解能光電子分光を行い、電子状態を調べました。この「共鳴光電子分光」というのはあるイオンの価電子状態を調べるのに有力な実験手法で、後で紹介するするようにNd
4f軌道の電子、Mn 3d軌道の電子といった特定の電子のスペクトルへの寄与を選択的に増大させるので、電子状態を元素選択的に調べる事ができます。
ペロブスカイト型Mn酸化物は巨大磁気抵抗効果を示すことから、純粋科学的興味のみならず応用面においても近年大きな注目を集めています。3次元ペロブスカイト構造(ABO3という組成、ここでMnはBに相当します。)をとるLaMnO3はMnイオンが形式的に+3価でd電子数は4.0となった反強磁性絶縁体です。しかし+3価のLaイオンを一部+2価のSrイオンに置換するとMnのd電子数は4.0という整数からずれて小さくなります。すなわちホールが注入されます。するとLa1-xSrxMnO3でx>0.15という組成では強磁性金属に変化します。このMn酸化物における強磁性は古くから二重交換相互作用によるものと考えられてきましたが、それだけでは説明ができないという説もあり最近再び研究が活発に行なわれています。一方、Laイオンをよりイオン半径の小さいNdイオンに変えたNd0.5Sr0.5MnO3
(x=0.5)は約160Kで強磁性金属−電荷整列反強磁性絶縁体転移を起こす事が知られています。この「電荷整列」は上記のLaMnO3の反強磁性体とは違うタイプ(CE型と呼ばれます)で、電荷・スピン・電子軌道の3つが同時に整列するという珍しい現象です。しかし組成が僅かにずれたNd0.53Sr0.47MnO3
(x=0.47)は電荷整列を示さず、低温まで強磁性金属です。 このようなMn酸化物にたいして光電子分光がこれまで行われていますが、強磁性金属−電荷整列絶縁体転移による光電子スペクトルの変化はこれまで観測されていませんでした。また、希土類イオンであるLa,
Nd等の電子状態は殆ど調べられていませんでした。そこで私たちはこれらの系に対して共鳴光電子分光及び高分解能光電子分光を行い、電子状態を調べました。この「共鳴光電子分光」というのはあるイオンの価電子状態を調べるのに有力な実験手法で、後で紹介するするようにNd
4f軌道の電子、Mn 3d軌道の電子といった特定の電子のスペクトルへの寄与を選択的に増大させるので、電子状態を元素選択的に調べる事ができます。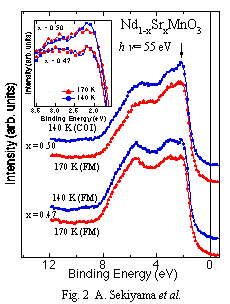 次に金属(Ferromagnetic
Metal, FM)−電荷整列絶縁体(Charge-Ordered Insulator, COI)転移を起こすNd0.5Sr0.5MnO3
(x=0.5)と電荷整列転移を起こさず低温まで金属であるNd0.53Sr0.47MnO3
(x=0.47)の両物質に対して、価電子帯高分解能光電子分光を光の励起エネルギー55 eV(波長に直すと約230オングストローム)、分解能45
meVで測定しました。実験はPhoton Factory BL-3Bで行いました。その結果のうち広いエネルギースケール(結合エネルギーでフェルミ準位からその下12
eVまで)のスペクトルFig. 2を右に示します。このエネルギースケールでみると第一印象としては両物質に違いはあまりなく、またx=0.5でも相転移によるスペクトル変化は大きくありません。しかし、結合エネルギー2.3
eVのピークをみるとx=0.5の温度140 K(絶縁相(COI相))では170 K(金属相(FM相))と比べるとシャープになっています。これは絶縁相でMn
3d電子が局在化した為と考えることができます。このような変化はx=0.47でははっきり見えません(挿入図)。
次に金属(Ferromagnetic
Metal, FM)−電荷整列絶縁体(Charge-Ordered Insulator, COI)転移を起こすNd0.5Sr0.5MnO3
(x=0.5)と電荷整列転移を起こさず低温まで金属であるNd0.53Sr0.47MnO3
(x=0.47)の両物質に対して、価電子帯高分解能光電子分光を光の励起エネルギー55 eV(波長に直すと約230オングストローム)、分解能45
meVで測定しました。実験はPhoton Factory BL-3Bで行いました。その結果のうち広いエネルギースケール(結合エネルギーでフェルミ準位からその下12
eVまで)のスペクトルFig. 2を右に示します。このエネルギースケールでみると第一印象としては両物質に違いはあまりなく、またx=0.5でも相転移によるスペクトル変化は大きくありません。しかし、結合エネルギー2.3
eVのピークをみるとx=0.5の温度140 K(絶縁相(COI相))では170 K(金属相(FM相))と比べるとシャープになっています。これは絶縁相でMn
3d電子が局在化した為と考えることができます。このような変化はx=0.47でははっきり見えません(挿入図)。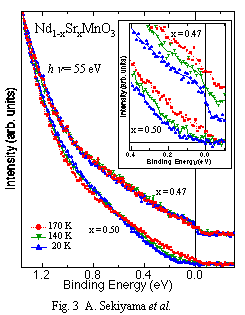 今度は物質の電気的、磁気的性質を主に決定づけているフェルミ準位近傍(結合エネルギー0
eV付近)における、測定温度を変えて測定したスペクトル(右図、Fig. 3)を紹介します。相転移を起こさないx=0.47では20 K, 140 K, 170 Kでスペクトルは殆ど変化せず、フェルミ準位のところでスペクトル強度が不連続的に0になりました(挿入図をみると分かりやすいのですが、この不連続性は温度が低いほど顕著になります)。実はこの「フェルミ準位における有限の強度かつ不連続的に強度が0になる」振舞いが、金属に見られる重要な特徴です。ひるがえってx=0.5のスペクトルに注目しますと金属状態である170 Kではフェルミ準位で有限の強度が見られます(挿入図)。しかし、絶縁体になった140
K及び20 K(転移温度は約160 K)ではその強度が著しく減少して殆ど0になっています。これは「電荷整列ギャップ」が開いた証拠といえます。また、同じ絶縁相でも140
Kと20 Kではスペクトルが僅かに異なり、フェルミ準位近傍の積分強度は140 Kの方が僅かに大きいです。これは140 Kでは電荷整列ギャップがまだ完全に開ききっていない事を示しています。20 Kにおけるギャップの大きさは少なくとも100 meV (0.1 eV)という大きさであることもこれで分かります。このようなCE型電荷整列ギャップが光電子分光で観測されたのは、この実験が世界で初めてです。また、この相転移を起こす組成に非常に近いNd0.53Sr0.47MnO3
(x=0.47)で低温まで金属的なスペクトルが得られたのもこの実験が初めてです。これらの事から、x=0.5ではMn 3d電子数が形式的に3.5と半整数になり電荷整列を極めて起こしやすくなっているところに、x=0.5からみて少しだけ電子が注入されたx=0.47では注入された電子によって二重交換相互作用が強くなり、金属的性質が復活していると捉えることができます。
今度は物質の電気的、磁気的性質を主に決定づけているフェルミ準位近傍(結合エネルギー0
eV付近)における、測定温度を変えて測定したスペクトル(右図、Fig. 3)を紹介します。相転移を起こさないx=0.47では20 K, 140 K, 170 Kでスペクトルは殆ど変化せず、フェルミ準位のところでスペクトル強度が不連続的に0になりました(挿入図をみると分かりやすいのですが、この不連続性は温度が低いほど顕著になります)。実はこの「フェルミ準位における有限の強度かつ不連続的に強度が0になる」振舞いが、金属に見られる重要な特徴です。ひるがえってx=0.5のスペクトルに注目しますと金属状態である170 Kではフェルミ準位で有限の強度が見られます(挿入図)。しかし、絶縁体になった140
K及び20 K(転移温度は約160 K)ではその強度が著しく減少して殆ど0になっています。これは「電荷整列ギャップ」が開いた証拠といえます。また、同じ絶縁相でも140
Kと20 Kではスペクトルが僅かに異なり、フェルミ準位近傍の積分強度は140 Kの方が僅かに大きいです。これは140 Kでは電荷整列ギャップがまだ完全に開ききっていない事を示しています。20 Kにおけるギャップの大きさは少なくとも100 meV (0.1 eV)という大きさであることもこれで分かります。このようなCE型電荷整列ギャップが光電子分光で観測されたのは、この実験が世界で初めてです。また、この相転移を起こす組成に非常に近いNd0.53Sr0.47MnO3
(x=0.47)で低温まで金属的なスペクトルが得られたのもこの実験が初めてです。これらの事から、x=0.5ではMn 3d電子数が形式的に3.5と半整数になり電荷整列を極めて起こしやすくなっているところに、x=0.5からみて少しだけ電子が注入されたx=0.47では注入された電子によって二重交換相互作用が強くなり、金属的性質が復活していると捉えることができます。